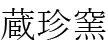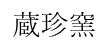美濃焼とは
よく美濃焼って何ですか?ということを聞かれます。
美濃焼は、他の焼き物産地である九谷・京焼・有田焼・信楽・備前などと多少異なり、1つの焼物の様式(スタイル)を持っていません。美濃(東美濃地方)で焼かれた器というのが一番わかりやすい表現でしょうか。代表的な織部焼・志野焼をはじめ、土ものだけでなく・磁器の産地でもあり、焼物の国内シェアは半分以上を占めます。
美濃焼のふる里は広く、岐阜県南部の東濃地方と愛知県境。主に瀬戸と隣接する土岐市、多治見市辺りです。もともと「美濃焼」とは明治以降に使われ始めた言葉で、15世紀頃は瀬戸と同様の器が焼かれていました。そして安土桃山時代に武将の茶の湯の文化とともに、茶人の好みを反映した芸術性の高い茶陶 -しっとりとした器肌の黄瀬戸・斬新な意匠の織部・白い釉薬の志野・漆黒の瀬戸黒茶碗など- が生み出されました。これが桃山陶です。
その後、江戸期から近代は日用雑器の産地でしたが、昭和になり桃山陶を再現した陶芸家ら(荒川豊三・北大路魯山人など)により美濃焼は注目を集め、現在でも多くの窯元・作家・量産工場など幅広い器づくりの人たちが活動をしております。
器の焼き・技法-その1・素地
現在、和食器として使われているのは、誕生順に炻器(せっき)、陶器、磁器の3つに大別されます。
まず備前、常滑、萬古、伊賀、信楽などが代表的産地である炻器(せっき)は、窯が造られるようになってからの焼物。成形後、乾燥させ、素焼きや施釉をせずに本焼きします。基本的に釉薬は掛かっていませんが、素地に透水性がない(水を吸収しにくい)ことと焼成温度が高いことから、硬く焼き締まり、水もれしないのが特徴です。
陶器は“土のもの”とも呼ばれます。吸水性のある粘土が使われ、この素地を素焼き→下絵付→施釉の順に行い焼成します。唐津・萩をはじめ美濃焼の代表でもある織部・志野などがよく知られています。 素地と釉薬との収縮率が違うことにより生じる貫入と呼ばれるひびが見所の1つです。
有田・清水・九谷・美濃など様々な産地で焼かれる磁器は、日本では17世紀前半に朝鮮陶工・李参平が有田で磁器原料を発見したことに始まります。ほぼ金属成分を含まない磁器が使われ、焼物ではもっとも硬く、吸水性はありません。1300~1400℃の高火度で焼かれ、薄手で素地が白く、たたくと金属的な音がするなどの特徴があります。
器の焼き・技法-その2・釉薬
陶磁器の表面を覆っているガラス状の被膜を釉薬(ゆうやく)、または釉(うわぐすり)と呼びます。ガラスと同じように硬く、耐酸・耐アルカリの優れた性質を持っています。釉薬をかけることを施釉といい、施釉によって器は硬度を増し、透水性がなくなって水もれや油じみを防ぐことができます。また、色と光沢による装飾的な役割も果たします。
釉薬の始まりは、窯の中で器にかかった薪の灰が高温で溶け、ガラス質になって付着した灰釉(かいゆう)で、偶然に見つけられました。釉薬の種類はさまざまですが、基本の成分によって灰釉(かいゆう)・長石釉(ちょうせきゆう)・鉛釉(えんゆう)の3つに分類され、さらに鉄や銅などの金属を加えていろいろな色の釉薬を作り出します。
素地に掛けた釉薬の色は、そのまま発色するわけではありません。釉薬や素地に含まれているわずかな金属が、窯の中の炎によっていろいろな化学変化を起こして発色します。酸素の供給が少ない還元炎なら青く、多い酸化炎なら黄色に発色するという具合です。同じ釉薬を使っても、素地の成分や施釉量、焼成法、燃料などのさまざまな条件で発色の仕方が異なります。
器の焼き・技法-その3・絵付け
釉薬の下に描くものを下絵付け(したえつけ)、釉薬の上に描くものを上絵付け(うわえつけ)と大別します。
下絵付けは、成形した素地を乾燥させ、1度素焼きしたものに直接絵付けをします。コバルト・鉄・銅などの顔料で描かれ、上から透明釉を掛けて、1200℃以上の高温で本焼きします。呉須と呼ばれる酸化コバルトで絵付けをすると藍色に、志野や絵唐津、織部などに見られる鉄の顔料で描かれたものは茶褐色から黒褐色に発色します。また、酸化銅で絵付けをして紅色に発色する釉裏紅(ゆうりこう)もあります。下絵付けは筆描きが一般的ですが、銅版・印判押しや、吹墨(ふきずみ)と呼ばれる手法もあります。
赤絵・色絵・五彩などの上絵付けは、本焼きした器の釉薬の上に筆で絵模様をつけます。鉄や銅・コバルト・マンガンなどの金属に鉛やソーダなどを加えて調合した絵具を使います。色数が豊富で、色がとばないよう、800℃前後の低火度で焼成します。
まれに下絵付けと上絵付けを併用する場合があり、伊万里の装飾の技法や色鍋島、美濃焼がこの手法の代表です。